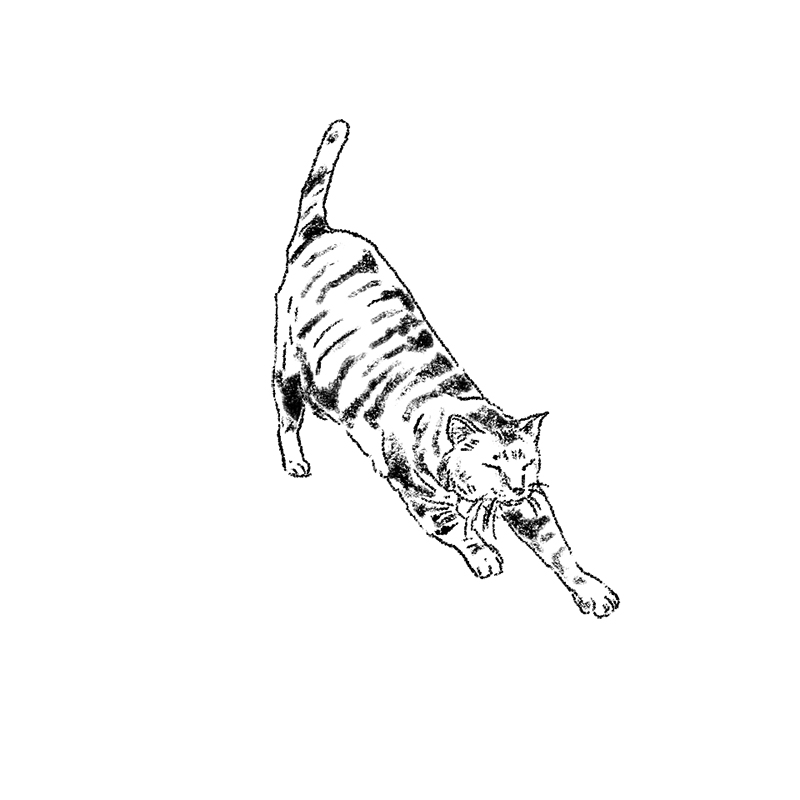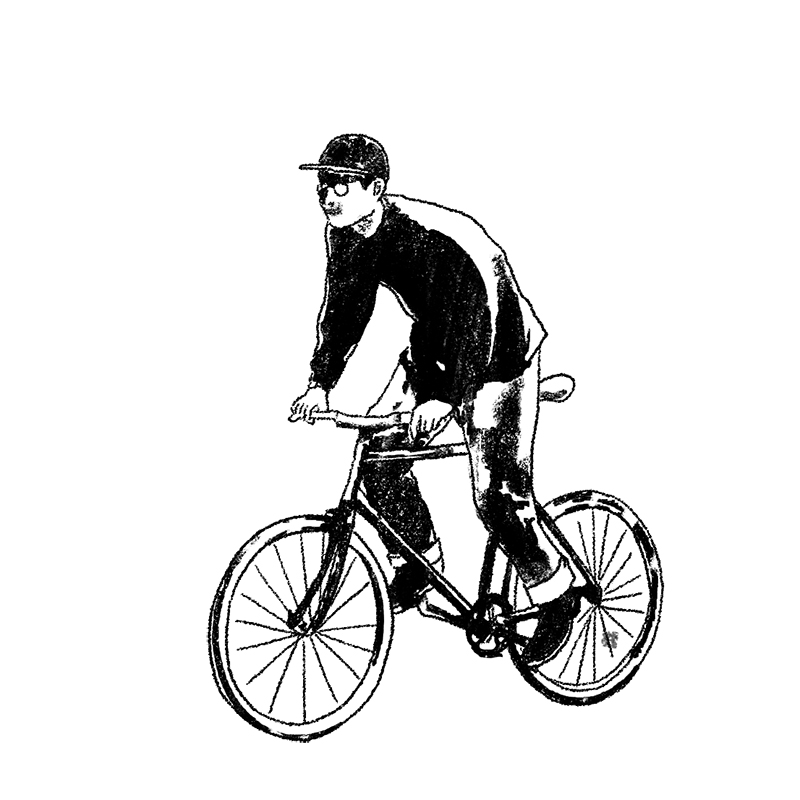はじめに
「世界に誇れる日常を生み出す」
まずこちらのPhilosophyをお読みください。
この「9つの日々のヒント」は私たちの判断基準としています。この積み重ねの先に「世界に誇れる日常を生み出す」ことができると信じています。このPhilosophyに共感いただけるかたと一緒に働きたいと考えています。
「今ここにあるものの見方を変えるチーム」
また、わたしたちはチームを「今ここにあるものの見方を変えるチーム」と定義しています。(Who we are?)谷中を中心とした地域に根ざし、地に足をつけた事業を行うなかで、身の回りの当たり前のもの、価値の無いと思われているものを、想像力をもって価値に変えていくことができるチームだと考えています。
求める人はこんな人・・!
- 私たちのコンセプトに共感し、愛をもった行動ができる方
(philosophyである「9つの日々のヒント」を基準とした積み重ねの先に、「世界に誇れる日常を生み出す」ことができると信じています。そのためには仲間に対する愛を、日々の言葉や行動に起こすことがとても大切。)
- 長期勤務が可能な方
(正直、1年以上は働いて欲しい……。基本的には、短期募集は受け付けておりません。少しでも多くの時間、過程を共に過ごすことで見えてくる、景色、奇跡がここにはあるから。
- ”いいアイデア”だけではなく、”良い工夫”の方を考えられる方
(いいアイデアもいいけれど、今ある場所・関係性・ものなどで、どうするか?もとっても大事。)
- 物事の過程、その先を想像することを楽しめる人
(何事も準備する時間は忙しいし、とても大変。でもそんな過程も仲間と、どう前向きに乗り越えて、考えるか当事者として歩める仲間でありたい。)
- 関わる相手に寄り添い、尊重し合える方
(スタッフ、お客さん、まちのご近所さん、業者さん、全国の生産者さん、アーティストの皆さん……。ここに関わる全ての”人”が大切で、欠かすことのできない仲間。いろんな人がいるから色んな意見があるのも当たり前。みんなの違いを、この場の魅力や強みに変えて捉えることを大切にしてほしい。)
向いてない人・・・
- 自分ごとになれない人
(日々起こる様々なでき事に対して当事者意識を持ち自分ごとに置き換えて考えることが大切。わたしには関係ないなんて、ちょっと悲しい。)
- マニュアルや、ルール通りに働くことが好きな人
(考え方、見え方、捉え方は人それぞれ。基本的ルールはあるけれど、1~10を教え0から学ぶ環境はここにはありません。自分で、みんなでより良い方法を考え、主体的に動ける人が向いています。)
- 想像力がもてない人
(ひらめきのアイデアも大事ですが、相手が何を考えているか想像できるかできないかってとっても大事。私たちはTEAMだから。)
- 他人の噂話や、陰口が好きな人
(一緒に働く仲間同士、誰もが肩の力を抜いてのびのびと自分らしく働ける環境を作って行きたい。マイナスな話は空気も悪くするし前向きになれないよね)
各部門の募集詳細